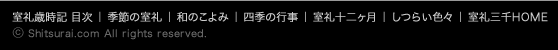|  十五夜の由来 十五夜の由来
旧暦8月15日の夜。
月見、名月、中秋の名月、芋名月とも呼ばれ、古くより観月の風習があります。 月見の風習は中国から平安時代に伝わり、貴族の間で宴が行われるようになったのが始まりとされています。
当時の宴は、詩歌を詠じ、管弦を主とした風流なもので、酒宴を伴うようになったのは室町中期といわれてます。現在のように供物をする様になったのは江戸時代に入ってから庶民の間に広まりました。
農民の間では、農耕行事と結びついて、収穫祭としての性格もあわせ持っていました。
昔から、十五夜の満月は、豊穣を象徴するものとして収穫の儀礼をとり行う大切な節目だったのです。 芋名月と呼ばれる由縁は、里いも(きぬかつぎ)などの芋類の収穫がこの日に行われていた為です。
 一昔前までは、十五夜の夜には、縁起かつぎの一つで人の畑に入って作物を盗んでよいとか、お供物を盗んでよいとかという風習が各地にありましたが、悪習として廃れた所が多い様です。
またこの日、月の出具合によって作物の豊凶を占うところもあります。 一昔前までは、十五夜の夜には、縁起かつぎの一つで人の畑に入って作物を盗んでよいとか、お供物を盗んでよいとかという風習が各地にありましたが、悪習として廃れた所が多い様です。
またこの日、月の出具合によって作物の豊凶を占うところもあります。
旧暦9月十三夜を豆名月、栗名月と呼び、片方しか見ないのは「片見月」と言って不吉なものとされていましたが、これは日本において江戸時代から始まった、特に都市部に多くみられた風俗です。
「中秋」と「仲秋」
中秋の名月の「中秋」とは秋の真中という意で旧暦(陰暦)8月15日をさしており、「仲秋」とは区別して使われています。旧暦では七月・八月・九月が秋にあたり、「仲秋」は秋三ヶ月の中の月、つまり旧暦8月全体のことをいいます。
|