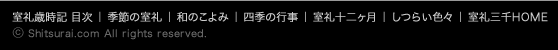|
月の呼称
朝夕の風に秋の気配を感じる旧暦八月。少しずつ秋が深まってゆきます。澄んだ夜空に月が美しい季節、古くから「中秋の名月」と呼ばれる旧暦八月十五日の月は、旧暦九月十三日の月とあわせてことのほか愛でられきました。
中秋の名月は別名「芋名月」、十三夜の月は「豆名月」「栗名月」とも呼ばれ、ともにこの時期に収穫される作物にちなんでいます。
このほか、月には満ち欠けに関する様々な呼名があります。
新月・朔
月が太陽と同じ方向にあり月をみることができない。陰暦一日。
二日月(ふつかづき)
陰暦二日の月。
三日月(みかづき)
陰暦三日の月。その細い形から月の眉、月の剣とも。
上弦(じょうげん)
新月から満月になる間の半月のこと。弓の弦が上を向いた形からついた呼名。
十三夜
満月の2日前。特に陰暦九月十三日を栗名月、豆名月、後(のち)の月とも呼ぶ。
小望月(こもちづき)
満月の前夜。待宵(まちよい)とも。
満月・望月・十五夜
満月。特に陰暦八月十五日の月を中秋の名月、芋名月とも呼ぶ。
十六夜(いざよい)
陰暦十六日の夜。月がいざよい(ためらい)ながら上がる様子を表している。
満月を過ぎ、だんだんと月の出が遅くなる。
立待月(たちまちづき)
満月の2日後。立って待っているうちに上がる月。
居待月(いまちづき)
満月の3日後。座って月の出を待つ。
寝待月(ねまちづき)・臥待月(ふしまちづき)
満月の4日後。月を寝てまつ。
更待月(ふけまちづき)
満月の5日後。夜が更けてようやく出る月の意。二十日月とも。
下弦(かげん)
陰暦二十二、二十三日頃。
満月から新月になる間の半月のこと。 弓の弦が下を向いた形からついた呼名。
「二十三夜待ち」といって陰暦二十三日の夜半過ぎに月待ちをすると願い事がかなうという風習が残っているところもある。
二十六夜(にじゅうろくや)
陰暦二十六日の月。
晦(つごもり)・三十日(みそかづき)
月の末日、みそかのこと。月隠(つきこもり)。
|